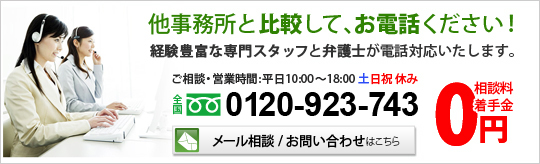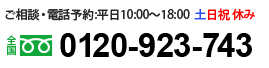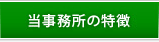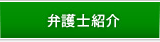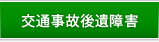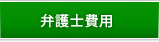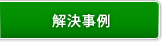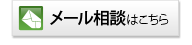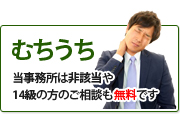傷害事故の損害賠償(逸失利益)
保険会社提示額と裁判所基準額は以下になります。傷害事故の賠償額は、表のA~Eの合計額です。
傷害事故の損害賠償
| A | 治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
| B | 休業補償 | 交通事故の被害者がケガをしたことにより,事故で減少した収入の補償 |
| C | 入通院慰謝料 | 交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料 |
| D | 逸失利益 | 本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
| E | 後遺障害慰謝料 | 交通事故の被害者が後遺症が残る傷害を負った場合には,そのこと自体に対し慰謝料を請求することができる。後遺障害の等級による基準がある |
1.後遺障害逸失利益
後遺症による逸失利益とは、交通事故の被害者が、後遺障害によって事故前の労働を行うことができなくなり、本来得られたはずの収入が失われてしまった利益を意味します。
この本来得られたはずの収入に対する損害を、後遺障害による逸失利益として請求することができます。
逸失利益は 原則として 基礎収入額に労働能力の喪失割合を掛けて、就労可能年数に応じた喪失期間に対応する係数を掛けて算出されます。
後遺障害逸失利益 =【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【中間利息控除係数(ライプニッツ係数)】
後遺障害逸失利益として認められる条件として、原則として後遺障害等級認定がなされたことが必要です。
基礎収入,労働能力喪失率,中間利息控除係数の求めかたをご説明いたします。
2.基礎収入
【給与所得者】
給与所得者の基礎収入は,原則として交通事故前の実際の収入額を基礎に計算します。
現実の収入が賃金センサスの平均賃金以下の場合であっても、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とすることもあります。また、30歳未満の若年労働者においては、全年齢平均の賃金センサスを用いることを原則としています。これは、年収の低い若年労働者の逸失利益が不当に低く計算されるおそれがあるので、賃金センサスの平均賃金を用いることで均衡を図ります。
【家事従事者】
家事従事者の基礎収入は、原則として全年齢平均賃金を基礎に計算します。パート収入がある兼業主婦であれば,実際の収入額と全年齢平均賃金のいずれか高いほうを基礎収入として休業損害を計算するのが一般的です。
【学生】
学生の基礎収入は、原則として全年齢平均賃金を基礎に計算します。
【失業者】
労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性がある場合には,原則として失業前の収入を元に基礎収入を計算します。ただ、失業前の収入が賃金センサスの平均賃金以下であっても、平均賃金を得られる蓋然性があれば、平均賃金額が基礎収入となります。
【高齢者】
就労の蓋然性があれば、原則として、賃金センサス年齢別平均の賃金額により基礎収入を計算します。
3.労働能力喪失率
労働能力喪失率とは,後遺症によって失われる労働能力を数値化したものです。労働能力喪失表を参考とし,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体的にあてはめて評価するものとされています。通常は比較的軽い後遺症以外では,労働能力喪失率表の喪失率に従って労働能力喪失率を認定する例が一般的です。
| 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
| 第1級 | 100/100 | 第6級 | 67/100 | 第11級 | 20/100 |
| 第2級 | 100/100 | 第7級 | 56/100 | 第12級 | 14/100 |
| 第3級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 | 第13級 | 9/100 |
| 第4級 | 92/100 | 第9級 | 35/100 | 第14級 | 5/100 |
| 第5級 | 79/100 | 第10級 | 27/100 |
4.労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は,原則として症状固定日から67歳までの期間とされます。ただ、交通事故の被害者が未就労者の場合は、18歳または22歳からが労働能力喪失期間の始まりとなります。被害者の職業,能力,後遺症の程度,機能回復の見込み等の状況により,上記の期間よりも短い期間に制限される場合があります。
高齢者については,上記の原則ですと労働能力喪失期間がめられなかったり,認められてもきわめて短期間になってしまいますので、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の1/2より短くなるような高齢者の労働能力喪失期間は、平均余命の1/2とされることがあります。
傷害事故の損害賠償に関しての詳細はこちら
交通事故の損害賠償に関しての詳細はこちら